|
|
|
教育福島0051号(1980年(S55)06月)-027page
|
|
|
随想
卒業式を終えて
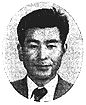
上田一夫
今年もまた、例年のごとく、卒業式が厳粛のうちに行われた。卒業生は、赤いカーネーションを手に、在校生の「さよならみなさま」の歌声に送られながら退場していく。
三年前、希望に胸をふくらませ、この場所で入学式に臨んだ彼女たちの今の心境はどんなであろう。
わが子のよりよい成長を願わない親はいない。できるなら子供の希望をかなえさせてやりたい。この学校でこのような教育をして欲しい。このような社会人になってほしい。などの期待と、新しい環境にうまく対応できるだろうか。よい友人が得られるだろうか。
などの不安の入り混った気持ちで、どの親も入学式に参列したのであろう。
組担任紹介の時、自分の子供の担任はどんな先生かと腰をうかしてまで教師席をうかがう親の気持ちがわかるような気がする。
高校生活への期待と不安を抱きながら入学してきた彼女たちが、三年間の生活の中で悩み、焦り、苦しみつつ成長していく過程において、自分は教員として彼女たちのためにどれだけのことをしてやれたかを自問自答してみるが、満足できるものは残らない。
式が終わり、最後のホーム・ルームが終わると、卒業生たちは職員室にあいさつにくる。
A子がくる。彼女には家庭における悩み、友人関係などでよく相談を受けたが、彼女の満足のいく、よりよい人生を歩むことのできるような回答を与えるほど勉強していなかった自分自身が悔まれる。浅い経験なるがゆえの思いつきの回答でしかなかったのではないか…
B子、C子と連れだってくる。B子は数学の成績はよくなかった。授業中の眼は、廊下で出会ったときの眼は、もっと親身になって、わかりやすく教えてくれるように語りかけていたのではなかったか。C子は時折り、反抗的な態度をみせたが、自分の心を理解してもらえぬ悲しさであったのではなかったか。
ともすれば、学習面、生活面での指導不足の責任を、生徒、親に転嫁し、己自身をみつめる心をなくしていなかったであろうか。そのような態度が、生徒、親の期待に反し、彼らとの距離を大きくしてしまったのではなかろうか。

心に残るものととて
彼女たちに握手を求められ、その手を力強く握り返してやるには、はなはだ自信がない。「よし、来年からは」と心で叫んでみても、むなしいものでしかない。自分には年度の終わるたびに反省があっても、彼女たちには高校生活は一回限りなのである。
「うちの子供は、あの先生でよかった」「あの先生にうちの子供を担任して欲しかった」という言葉をよく耳にする。他方、「生徒は教師をえらべない上とはよくいわれるが、教職にあるものとして、社会の状況が良くなかろうと、たとえ校務が忙しかろうと、自分の担任する生徒が、どのように生きていったら幸せを得られるかを真剣に考え、生徒に対していつ、何を、どのように手をさしのべていくかを考えるのが教師の最低限の務めではないか。
校舎内には「螢の光」のメロディーが静かに流れている。
(福島県立須賀川女子高等学校教諭)
|
|
|