|
|
|
教育福島0135号(1988年(S63)11月)-010page
|
|
|
たいと考え、本主題を設定した。
二、研究内容
(一) 指導内容の重点化をどう図るか。
(二) 指導過程をどう工夫するか。
三、研究の概要
(一) 指導内容の重点化を図るために、単元の指導計画の作成を.工夫する。次の手順により、本時は、児童に何を身につけさせるか、その重点を明らかにする。(資料1)
(1) 学習指導要領の内容を基に、教科書の内容を検討し、単元の指導のしくみをおさえる。1)
(2) 本単元の指導内容の前提となる基礎的事項を明らかにする。2)
(3) 本単元の指導について目標分析をする。3)
(4) 発展を明らかにする。4)
(5) 学級の児童の認識過程を想定し、単元構成を工夫する。5)
(6) 前提テスト及び事前テストから一人一人の習得状況・観察等から学習状況を把握し、実態を基に時限ごとに指導の重点に◎印を付して明らかにする。6)
(二) 指導過程を工夫する。
(1) 学ぶ力を育てるために授業の基本過程を明らかにする。(資料2)
(2) 学ぶ力を育てるための授業の基本過程に基づく授業展開のモデルを組む。(資料3)
(3) 展開のモデルによる授業の実際
1)「課題をつかむ」段階
学習への興味関心を引きつけ、意欲を高めて、いかに学習へ引き込むかがポイント、問題場面の設定がその鍵を握る。
課題をとらえる訓練
○これまでと同じところや違うところを見つける。
○ふしぎなところを見つける。
○困ったことを見つける。
○知りたいことを見つける。
問題場面設定の例
三年(円) 課題「円の中心を見つけるには、どうするか」
おもちゃの自動車を走らせる。自動車が走らないのは、車軸を指す位置に問題があることに一目で気づき、円の中心を見つけて走れる自動車にしょうとして学習が展開する。
2)「見通しをもつ」段階
資料1 指導内容の重点化を図る 算数科「立体」指導計画〈第6学年〉
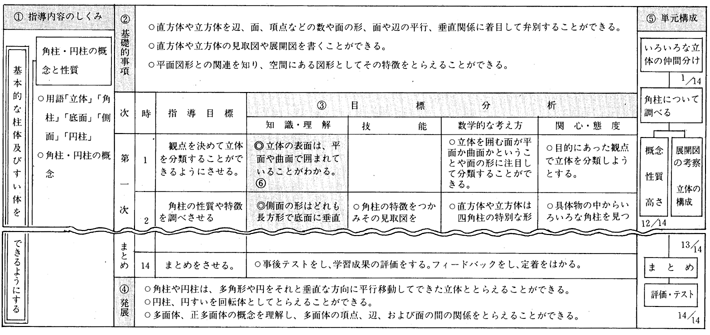
資料2 学ぶ力を育てるための授業の基本過程
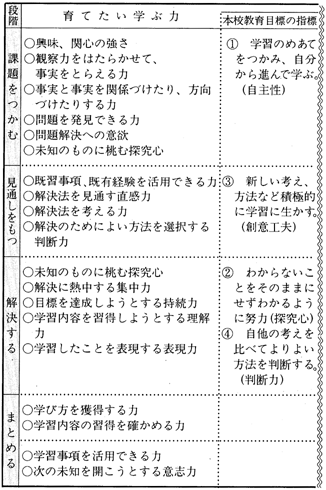
|
|
|