|
|
|
教育福島0146号(1990年(H02)04月)-027page
|
|
|
すると、せっかくの花も台無しになったり数が少なかったりなど、よいものが望めない。品種の特徴を知り、適切な時期に適切な手を施してやることが基本だ。忙しさにかまけて手入れを怠るとそのツケはかならずやってきて、心が痛む。
「植物も、毎日、“おはよう”と声をかけてやると、違うんですよ」と、やはり花の好きな知人がいった。すべてのものに、心をかけることの重みが、そこにある。窓辺の蘭の鉢を眺めながら、一人一人の生徒の個性を掴み、必要な時期に、適切な援助と助言を与えながら、その能力を十分に伸ばしていく教育の重みを、感じている。
(県立会津女子高等学校教諭)
一枚の色紙
高橋寛紀

「最下位」--これが私のマラソンヘの道、第一歩であった。教職三年目の夏、自分の若さに「何とかなる」という確信をもった挑戦でもあった。しかし、緊張のための睡眠不足と三十度を超す炎天下にあり、八キロ地点から記憶不明。意識が回復した時は、頭に冷タオル。救護員の制上を振り切り、どうにか完走。途中棄権者もいたが、この最下位が走る意欲の原点となった。
運動を大の苦手とする私に、マラソンの芽を育ててくれた東和町から二本松に転任する時一枚の色紙が届けられた。そこには、町駅伝で教員チームとして共に走った下重選手の字で「我慢」と書かれてあった。殺風景な教室に何気なくその色紙を飾り、当時三年生の子どもたちに、作文と合唱とマラソンを学級の核としてがんばろうと話した。しかし、作文や合唱とは異なりマラソンは決して東和町でのようには充実しなかった。新しい土地で芽を育てることは、時間のかかることだった。
その年の秋、若いうちにフルマラソンに挑戦しようと親友のSと山梨県河口湖に行った。五時間の制限時間内に二人とも完走。冷たい雨の中を走り続け、自分の身体が自分の身体と思えぬほどに疲れ果てただけに、二人で「もう走りたくない」と言いながらも目から光るものがあり声ははずんでいた。
そこで学んだものは、物事をやりとげた充実感。どんな人間でも長い時間我慢して取り組めば何かはできるということ。そして、マラソン哲学は、教育現場に生かされるということである。
教室に戻ると、あの下重選手の「我慢」が真っ先に私の目を釘付けした。どんな子どもでも我慢すれば走れるのだと、私に語るかのように。私は技術指導ばかりでなく、どの子も走ることに喜びを感じ、更に走ることが生活に生かされるよう考えるようになった。翌年の二本松市民マラソンは大雪で中止。教室で「延期でなく中止だ」と話すと涙をためてくやしがる子どもたち。この涙は、夏の東和ロードレース全員参加・全員完走へとつながった。
一方で、子どもたちは着実に走る喜びと技能を身に付け、県内のマラソン大会でトップクラスの成績を収められるまでに成長した。地域から、走ることを通して地区民の回結をと「二本松岳下ランナーズクラブ」が設立されたのは、一生懸命走る子どもたちに対する大人の感動の表れである。また、大会参加によって相馬や会津地区の子どもたちとふれあいが深まり、手紙や写真での交流も知らない間に広まっていった。更には、地域の活性化が青東(青森・東京)駅伝出場選手との定期的練習や中学校との連携強化にも功を奏していった。年一回のリレーフルマラソンも恒例行事となり、世界記録まであと五分と迫った。
若さにも限界はあるが、年一回のフルマラソン完走とランナー育成に情熱を燃やそうと、下重選手の「我慢」を見るたびに心を新たにしている。
(二本松市立岳下小学校教諭)
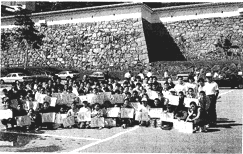
二本松市民マラソン大会で活躍した子どもたち
|
|
|