|
|
|
教育福島0184号(1995年(H07)01月)-029page
|
|
|
たさびしさが会場に広がっていった。授業や部活動、友人との語らい、さまざまな行事等を見つめてきた校舎は卒業生のたくさんの思い出をしみ込ませていたのであるが……。
同級会も終わりに近づき、幹事から小さな記念品が配られた。それを見た友の口から「あっ」という声がもれた。そこにあったのは、今、みんなの心の中に描かれた木造の校舎の姿であったのだ。小さなテレホンカードの校舎は、目の前に大きく広がり、私たちの心を再び思い出の世界へ引きずり込んでいった。そして、テレホンカードを手に、最後に校歌を歌ったが、それは楢原中学校の校歌であった。
ということで、私にとってはちよっと複雑な思いの「母校」なのである。この校舎で過ごしたことはないけれど、私と下郷中を結びつけるものが、今も残されている。それは、職員室前の廊下に掲示されている卒業生の写真である。第一回から現在までのすべての卒業生の姿がそこにあるのである。もちろん、十五歳の私もそこにいるのである。
学校を訪れるお客様や父兄や生徒たちが、その写真を見ていることがある、昔の自分を探したり、兄弟を探したり、母親を探したり。そこは人それぞれの思い出の世界への入口のようでもある。
十五歳の私に見つめられながら、今日もまた一日が始まる。「母校」での教師としての一日が……。
(下郷町立下郷中学校教諭)
思いやりの宝
荒由利子

「健康で、積極的に、そして根気強くなければならない。」障害児者親の会の会長さんのことばだ。
毎年生徒たちと障害児者の皆さんとのふれあいを持たせていただいている私が、毎回身を引き締めて聴くことばだ。そのことばには、余裕がないという深刻な叫びが年毎に強くなっている。親の会の皆さんの年齢が老齢期となり、自分の老いの不安と介護の限界を感じる我が子への心配が伝わって来る。親だから当然と一言で片付けられるだろうか。他人事だと聞き流せるだろうか。
いろいろな障害を持つ人たちが本当に安心して入所出来る施設は、成人に達するとめっきり少なくなる。また施設の生活に浸ると、外部の生活との交流は出来にくくなり、狭い生活範囲だけで終ってしまっている人の何と多いことだろう。
一人ひとりの子供たちの幸せを願うのは皆同じだ。ハンディを持つ子供たちの力を発見し、それを伸ばしてやるためには、親だけでは限界を生じて来るので多くの人の協力が必要である。私たちが自然なふれあいをする中から、それの手助けとなることもあるのではないか。普通のふれあいこそが真の福祉となるのではないだろうか。そしてそれは、障害を持ちながら懸命に生きている人たちにとっても共通な思いのはずだ。
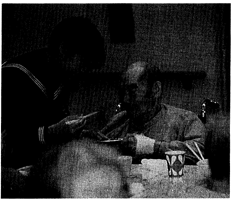
高校生と共にこの気持ちを実行に移そうと試み、ボランティアを始めてもう二十年が過ぎた。今でこそボランティアということばを誰でも理解し、受け入れられているが、当時は奉仕活動と呼ばれ、教育現場から生徒を連れて行く事に対して慎重論が多く、実行するまでには難しい問題があった。
私が小学生の頃には、在宅障害児者が多く、教室にはいつでも入って来れるようにと机と椅子が置かれ、担任の先生の対応は大変寛大であった。そして障害を持つ友から人間本来のやさしさを教えられた。こんな日常生活の中での気負わないノーマライゼーションがたくさんあった。現在は以前よりずっと社会福祉が充実されて、その進歩の早さには驚くものがある。でもそれに伴う人としての心のふれあいをも育てることが必要だと思われる。
ボランティアに参加する高校生は家庭科の男女共修に伴い、男女共に増加している。この活動はあくまでも自主・自発活動でなければならないが、彼等の多くはそのきっかけを必要としている。だから呼びかけは
|
|
|