|
|
|
福島県教育センター所報ふくしま No.19(S50/1975.1) -003/026page
|
|
|
図 4
III 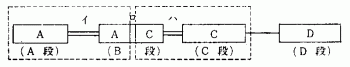
IIIのような場合,B段は前段とはAという内容でつながり,後段とはCという内容でつながる。B段の中のAとCの結びつきロが,その強さにおいてイ,ハよりも劣る時はIIと同じであろうが,逆にロがイ,ハより強い時はB段は分裂してしまう。
さらに,B段の中にA,B,Cの内容が混在してくると次のようになる。
図 5
IV 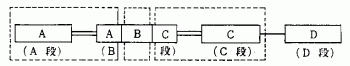
要するに,III,IVのモデルに見られるように,文章段落のひとつを分割しなけれぱ意味としてのまとまりをつけられないということがおこる。
そこで,III,IVのB段のような,前段にも後段にもまとめにくく,それでいてつながりのある段落を「橋渡し」的なものとして考えてみたい。これをBridge‐paragraphと呼ぶことにする。
「つなぎの段落」という考えは従来もあったようであるが,それは文章全体の本筋に余り関係ないこととして軽く扱われ,いわゆる「意味段落」にまとめていく時に,無造作にどこかへ含めてしまうことが多かったのではなかろうか。だとすれば,それはBridge‐paragraphというよりJoint‐paragraphというべきものであろう。次のVはJoint‐paragraphでありVI,VIIがBridge‐paragraphである。
図 6
III 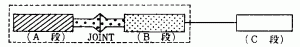
図 7
VI 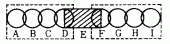
図 8
VII 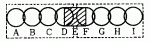
文章は改行ごとに切り離されたものではなく,段落間に何らかのつながりがあるわけであるから,当然,VI,VIIのように考えるのが段落の連接モデルとしてはふさわしいと思う。
Bridge‐paragraphは,前後をつなぐ(Joint)というだけでなく,文章の筋道にある方向を与えるものということができる。だから,いずれかの段落にこれを含めるよりも,独立した段落として考えていくことが,文章を大きくまとめていくことを自然で無理なくさせるいき方といえる。そして筆者の書く過程における段落意識が,改行された「文章段落」の中に見いだせることを考えれば,文章全体の筋にある方向を与えているBridge‐paragraphは「筆者の段落」にせまるためには重要な部分だと言うことができよう。
4. Bridge‐paragraphと「筆者の段落」
具体例でBridge‐paragraphと「筆者の段落」との関係を考えてみよう。(紙面の都合上,部分掲載。実際の文章の段落は( )で示された番号による。)
(2)の点線の部分は(1)に含めてもよさそうである。とくに第1行はかなり(1)と密着している。ところが,(2)の後半の囲みの部分は(3)への密着度が高い。(2)をBridge‐paragraphとして筆者の段落意識を読んでみよう。
こうしてみると,(1)と(2)の間を筆者がどうしてわけたのかがはっきりする。なるほど,文のつながりでいえば「それからだんだん……それはとうていむりであって……」の接読語,指示語から考えて点線のようにわけてしまいたくなる。しかし,筆者がここで改行したのにはそれなりの理由が内在していたはずである。
改行の焦点となっているものは「将来の道がわからない。」ことと「わかれ道が見えてくる。」こととの対比である。筆者は「人間以外のもの」に将来の道を探すことと「人間」に将来の道を求めることとをはっきり区別しようとしているのである。その意識が(1)と(2)とを区分させたのであろう。そして,「人間」の中でも地位,肩書きを望むことは,「人問そのもの」の姿への希望ではなく「機関車・飛行機」を望むことと大差はないのだという意識もあって,それを否定したところに論旨の展開をもとめている。
|
|
|