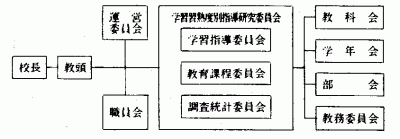生徒の多様化に応じた学習指導法の研究
一人ひとりの学習の成立をめざして
福島県立須賀川女子高等学校
1. 主題設定の理由
生徒の実態と地域や父母の要望をふまえ、生徒一人ひとりに学習参加の喜びを見いださせ、個性と能力の十分な伸長を図る学習指導法と教育課程のあり方を研究する・そのため・すべての教科科目で、「一人ひとりを積極的に参加させる学習指導法」と「個性と能力を伸ばす教育課程の研究」を具体的なねらいとした。さらに授業においては「生徒が目的意識を持って主体的に参加する学習活動を展開するために、学習習熟度に見合ったプログラムと指導法の研究開発」をねらいとし、一斉指導、グループ指導、習熟度別講座制等の学習形態の中で、多様化に対応できる学習指導法の研究を進める。最終的にはすべての生徒が個性を豊かに発揮し、主体的に学習に取り組みうるように変容してゆくことを期待して、この主題を設定した。
2. 研究内容
この研究を3つの分野から推進する。それぞれに委員会を置き、当該分野の研突を深める。
|
(1) 学習指導法の研究(学級指導法研究委員会) |
|
|
-
本校が過去に実施していた学力別指導に検討を加え、今後の研究の参考にする。
-
一人ひとりが積極的に参加する学習指導法の研究をする。
-
学習内容の習得を確かなものとするために授業内容の評価を研究する。
-
習熟度別学習集団を編成する場合に予想される問題点を究明し、望ましい学習集団の編成について研究する。
|
|
(2) 教育課程の研究(教育課程研究委員会) |
|
|
-
本校の現行教育課程の間題点を検討する。
-
習熟度別学習集団と自然学級編成の場合の教育課程について研究する。
-
習熟度別学習集団を設けた場合の教育課程研究の成果をふまえ、昭和57年度実施の新教育課程の資料を作成する。
|
|
(3) 調査・統計および資料収集(調査統計委員会) |
|
|
-
生徒の意識・実態調査を行う。
-
習熟度別学習集団を編成実施する場合、生徒・父兄への趣旨説明等を行う。
-
研究推進のための各種資料の収集、調査を行う
|
3. 研究体制
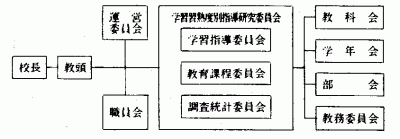
4. 「習熟度」のとらえ方
生徒の学習内容の習熟の程度というのは、生徒が努力次第で向上する余地のある動的な習得理解の程度、熟練の程度を表したものであつて、能力を固定的にとらえ、生徒を一定の尺度で優劣に区別し、各々異なる指導を行う差別的教育ではない。従って、習熟度を単なる能力の差とは考えずに、知識・技能等の理解の仕方、速さ、定着度、熟練程度等の概念のうち、主として、生徒一人ひとりの基礎学力がどの程度定着しているかの度合いとしてとらえた。そして基礎挙力については、さまぎまな考え方があるが、発達段階からみて、後の発達段階の基礎となる前の発達段階の学力ととらえて共通理解を図り、その上で研究計画をたてた。
5. 研究計画
|
|
年 月 |
研 究 計 画 |
|
第1年次 |
54.4〜9 |
・ 研究体制確立・研究主題設定
・ 調査分析・教科の研究主題設定 |
|
10〜12 |
・ 実践 I (自然学級の中での実践) |
|
1〜3 |
・ まとめ、反省、中間報告、計画修正 |
|
第2年次 |
55.4〜8 |
・実践 II (習熟度別学級集団をとり入れ実践)
・ 中間反省・部分的反省 |
|
9〜12 |
・実践 III (実践 II に基づき一人ひとり |