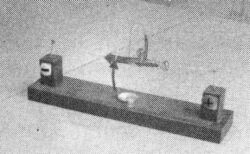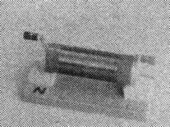福島県教育センター所報ふくしま No.73(S60/1985.10) -035/038page
を曲げて台足をつけ,鉄粉をまいて,3V,10Aを流して写真のようによくわかった。
6 導線の電流による磁界と磁針の向き
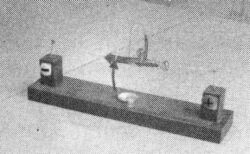
写真のように木の台に釘をうちつけ,針金を張り,マグネットでプラス、マイナスをどちらにも変えられるようにして,磁界の向きは針金で輪をつくり目玉クリップにハンダ付けして電流の向きによる磁界の向きを変えられるようにした。また,電流の向き,右ねじの標示はマグネットシートを形に切りとって導線に標示できるようにした。これによって電流の流れる向きと磁界の向きが,磁針が導線の上下どちらにあってもわかるようになった。正答率97%であった。
7 コイルのN極の向き説明器

今まで,授業をしてコイルによる磁界のN極のできる向きを教えるのにいろいろ試したが,電流と同じようによく理解されないので模型をつくって指導した。針金では細いので,ビニールパイプに針金を通してコイルをつくり,台にとりつけ電流はプラス、マイナスどちらでも変えられるようにマグネットでつくり,電流の向きと右ねじの標示をマグシートでつくりコイルにつけられるようにした。6と同じように磁界の方向を針金でつくり目玉クリップにハンダ付けし,どのような向きの電流にでも変えられるようにして,コイルの鉄心のある中側の磁界の矢印のさす向きがN極と指導した。これによると100%N極の向きがわかるようになった。1か月後テストしてみても97%の正答率であった。
8 誘導電流の指導

7で使用したコイルの模型を誘導電流に利用した。コイルを縦にしても倒れないようにしてN極を近づけると反ばつするN極ができる。このことからN極ができるときの電流の向きを考えさせ,誘導電流の向きを理解させた。この指導でも97%の正答率で,1か月後も97%の正答率であった。
9 磁化器
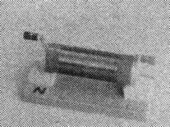
誘導電流の実験をするのに棒磁石や磁針の磁気が弱くなっていたので5のあまりのエナメル線で写真のように製作した。
3 おわりに
以上,9点の自作教具を紹介したが,この教具は先生が製作したのだと知らせると,「ほう」という驚きのことばとともに,実験に手を出さなかった生徒も進んで観察実験に参加し,課題解決にあたるようになった。また,授業がおもしろく,よくわかったという満足感,充実感が見られた。
本校では,生徒の実験カートのほかに「創意工夫による観察実験カード」をつくり,生徒自ら考え,創意工夫して観察実験できるようにしている。
教師のアイディアを生かした自作教具を活用するとともに,生徒のちょっとしたアイディアをとりあげ,ほめ,助言し,観察実験させるようにすると,授業に活気がみち,生徒も意欲的になってくる。
今後も,アイディア(創意工夫)を生かしたよくわかる授業の創造に努めていきたい。
掲載情報の著作権は情報提供者及び福島県教育センターに帰属します。