|
|
|
福島県教育センター所報ふくしま No.88(S63/1988.10) -012/038page
|
|
|
2.学習形態と課題追究のさせ方
問題解決的学習により課題解決の過程を通して成就感・満足感を体得させるためには,自分なりにまず課題解決ができる必要がある。そのためには,操作的活動を積極的に取り入れるとともに,ヒントカードを活用したり,更に学習形態としてはグループ学習を導入して小集団による学習効果を上げることが必要になってくる。
自力解決できない子供,全員の前ではなかなか自分の考えを発表できない子供に対して,全体学習に入る前に小集団による学習をする。自力解決できなかった子供もちょっとした助言により,解決方法の糸口がつかめたり,全員の前では話せない子供も自分なりの考えが持てたりして,話し合いに参加できるようになる。準備なしに全体で話し合うのと違い,それぞれの考えを持って話し合いに参加するため,お互いに自分の考えを主張でき話し合いも活発になる。
このような小集団学習によって,自分がどこまで分かり,どこでつまずいているかを知り,課題解決ができるとともに,自己の存在感が感得され学習意欲が高まっていく。
次の図は,小集団学習を全体学習に組み入れ,課題追究をさせた工夫の例である。
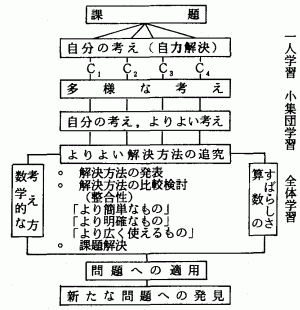
このように,よりよい解決の方法を追究する過程,一般化の過程,新しい問題の発見の過程を通して数学的な考え方が養われていく。
また,「考えるというのは,どうすることなのか」といった考えや考え方を,解決過程を振り返らせていく過程で体験的につかませていきたい。
3.年間を見通した評価の工夫
一単位時間内で教師が意図した内容のすべてを理解し,全員が目標に到達することは難しい。
そこで,一人一人の能力・適性を考慮し年間を見通した評価計画を作成し,適時,個別指導等を行い,当該学年の終りまでには必ず全員に既習内容を定着させる指導を工夫した。次の事例をもとに述べてみたい。
(1)評価の年間計画の作成
特に,形成的評価と総括的評価を行う時期とねらいを考え,年間の見通しを立てて評価を実施するようにした。
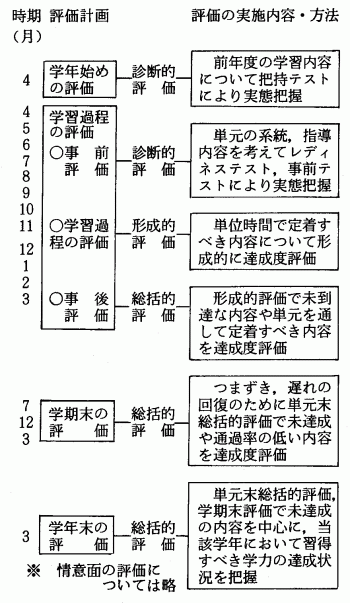
|
|
|