|
|
|
福島県教育センター所報ふくしま No.89(S63/1988.12) -016/038page
|
|
|
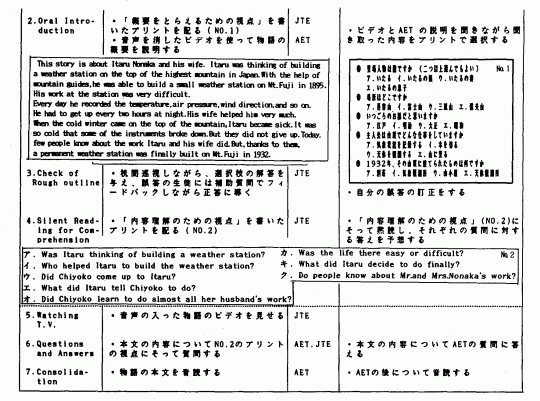
※(第1時では,指導過程の1〜4まで,第2時では,5〜7までやることが望ましい)
6.指導上の配慮事項
(1) 「概要」を把握させる手段や方法はいろいろ考えられるが,ここでは導入時に新出語句を扱わず,AETのOralIntroductionによるRough outlineの把握を試みる。
(2) 英語学習は場面設定が大切である。そこでビデオにより,その場面設定を明瞭にする。ビデオの使用によって学習への意欲づけを図りたいと考えるからである。
(3) 内容理解を確かなものにするため,「概要をとらえるための視点」を提示し,それによってポイントをおさえた読みができるようにする。このアプローチは生徒に「読むこと」の前段階として目的を持たせることにより,生徒を積極的に「読むこと」に取り組ませるのに有効であると考えた。
(4) 内容理解のCheekには,「内容理解のための視点」に基づくQ&Aを行う。ここでは,AETが中心となるが,生徒が誤答した場合は,内容理解を確認しつつ英問英答や和問和答も適宜使いわけながら,JTEが正答に導くように配慮する。(JTEの複数の補助発問が必要である)
7.おわりに
ここで述べた具体例は,略案であり,あくまでも試案である。生徒の実態により,Musicの導入などいろいろな方法が考えられる。
現在行われているティーム・ティーチングによる指導例の多くは,「聞くこと,話すこと」に重点を置いたものであるが,AETを活用する意味からも,今後は,「読むこと」,「書くこと」の領域での利用も含めた指導方法や指導過捏を研究開発していく必要があると思われる。
|
|
|