|
|
|
福島県教育センター所報ふくしま No.91(H01/1989.6) -010/038page
|
|
|
待できるかということから判断する必要がある。
<子どもに対して>
子どもが自己理解を深めていくことができるようにする。その時は、雰囲気を和らげ、結果に ついてどのように感じ、受けとめているかを考えさせる。決して、断定するとか、誤解を与えるような言い方はしない。
<親に対して>
考え方や態度を変ええもらいたいと願う場合に伝える。その時は、常に親と共に考える姿勢を保ちデータそのものを知らせるのではなく、生活状況との関連でとらえ、親としての適切な対応に気づかせる。
3.活用事例
(1)対 象 中学3年生 男子
(2)問題行動の概要 (不登校)
・受験勉強の時期を迎え、10月頃から頑張って机に向かうが根気が続かず、このままでは皆から遅れてしまうというあせりが出てきた。
・朝、登校意欲をみせるが、腹痛などの身体症状を訴え、登校できない。
(3)資料
・(幼児期) 3才まで祖母に預けていたので他の子どもたちとの交流は少なかった。登園を嫌がることが多かった。
・(小学校) 落ち着きがない。不器用である。5年生頃、首チック症状がみられてきた。
・(中学校) 友達はほとんどいない。3年になって、長時間手を洗う強迫行為が出てきた。
(4)指導援助の過程
1第一回目の面接
既存の資料からも、人間関係を上手に取れないことが大きなつまずきとなっている。また、本人は学習が思うようにいかないことも不安としてあげている。
そこで、人間関係がとれない原因はどこにあるのか、YG性格検査を行い、その行動傾向を探った。
資料1〔本人のYG性格検査〕〔E〕型
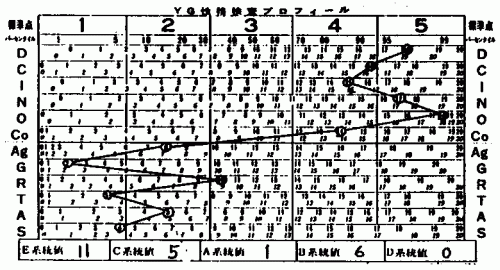
・引っ込み思案で対人閉鎖症がある。
2第4回目の面接
近所では小さいころから「すなおな子」と見てくれていた。しかし、母からは「むずかしい子」で、妹のことはよく褒めるが、本人を褒めるのは苦手だった、という。
本人を受容し、共感的に理解しようとする姿勢が母親から感じられなかったために、「親子関係診断テスト」と「エゴグラム」を実施し、今までの養育態度について話し合った。
資料2〔母親の親子関係診断テスト〕
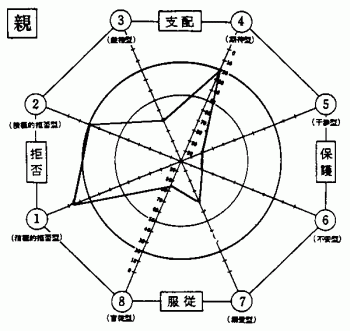
・期待をかけているが子どもとのかかわりは弱い。
資料3〔母親のエゴグラム〕
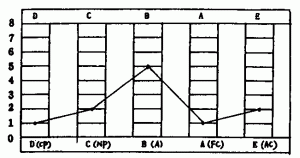
・子どもたちととけこんで遊ぶことが苦手。
|
|
|