|
|
|
福島県教育センター所報ふくしま No.116(H07/1995.11) -038/042page
|
|
|
3. 「個人成績カルテ」の導入から
各段階において自分の理解度を知り,弱点解消のため「何を,いかになすべきか」を生徒各自が考え,自ら課題を解決するのに有効であった。
4. 「事前・事後・把持テスト」から
把持テスト終了後.生徒を3グループ に分け反省をまとめた《資料4》。下位の生徒も基礎が定着し,楽しく学習していたようである。また,《資料5》の変容のグラフから問題項目2,3については,高い有効度を示している。しかし, 項目5,6の応用力となると有効度は低い。特に,読解は生徒達の感想にもあるように「単語力」の不足が,伸張度また有効度の低い原因の一つであろうか。しかしながら,このような指導を展開していけば,本校生の弱点である英文読解力の向上にもつながると考えられる。
《資料4》把持テスト終了後の感想
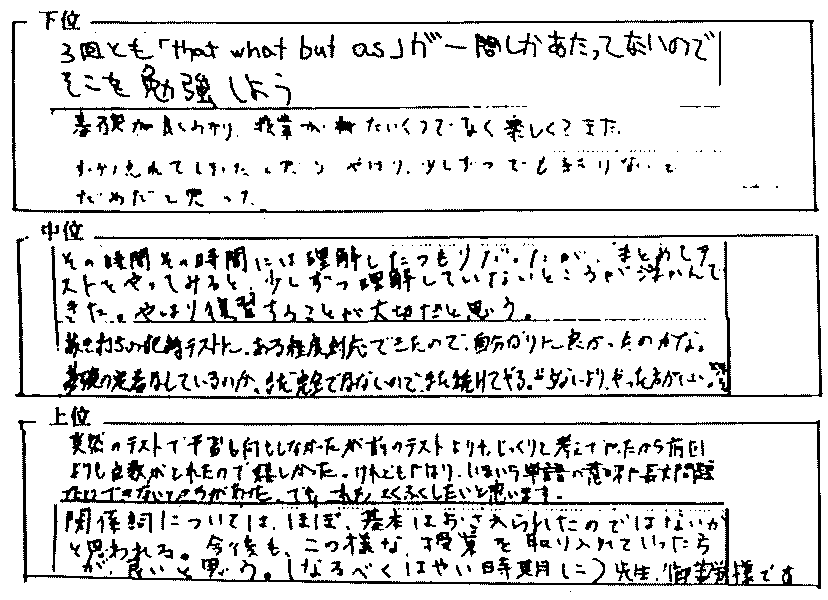
V 研究のまとめと今後の課題
1 研究のまとめ
文法力の向上には「教材の精選と段階化」「個に応じた指専」は有効である。今回の研 究で「関係詞の理解」は深まり弱点解消になったと判断できる。しかし,読解力が向上し たという実証は得られなかった。その理由として,次のような事が考えられる。
◆英文読解カは,語彙力の増強や他要素が関連し,一朝一夕で向上するものではない。
◆事前・事後・把持テストの英文の難易度にバラツキがあり,正確で客観的なデータが得られず十分な検証ができなかった。
2 今後の課題
(1)効率的な教材の精選と段階化及びその実践のために,TT方式を導入する必要がある。
(2)習熟度別授業を取り入れ,学力差に応じた指導の充実を図る。
(3)授業がわからないことは,何よりも苦痛 である。本校の成績上位者と言えども,基礎・基本に欠け「円錐型」の学力ではなく不安定でもろい剥落学力である。学ぶ意欲と基礎を定着させる授業を展開することである。
※参考文献
- 高校新基礎英語 桐原書店
- 英語教育 大修館 1993年別冊
- 話題源英語(上) 東京法令出版
- 基礎英文法問題精講 旺文社
- 平成5年度教研法講座 研究報告書 福島県教育センター
|
|
|