|
|
|
教育福島0115号(1986年(S61)10月)-020page
|
|
|
会であった。
3) 事後交流
事前交流、交歓会と二度の交流を実施し、相互に理解することであたたかい気持ちをもって接することができるようになった。
二月四日常磐ハワイアンセンタ一で水遊びを中心に、体で触れ合い裸でつき合える交流を求め、さらに植物園の見学など、生活経験の拡大とより多くの人々との交流を深め、社会性の向上に役立たせるよう計画された。
まだまだ寒い日が続くこの頃二時間三十分のバスの車は、マイクを手に、子どもたちが、次々と歌い出す。水着に着替えてプールヘ、プールに入れなかった子どもたちは、バナナの木や小鳥、ピラニア、エリマキトカゲ等がいる植物園を見学し、多くの人々と交流を深めて、無事帰途に着いた。
三 交流教育の成果
(一) 交流前と交流後の児童の変容
生活経験を広め社会性を養い好ましい人間関係を育て、集団への適応力を高めるなど、協力校児童には、よく理解してもらい仲良くいっしょに活動するというものであった。
本校児童は、地理的環境にあっては、隔離されたような場所で、自然な状態での交流は、今までに経験することはなかった。しかし、今回の交流により、お互いにさまざまな形でかかわり合いながら接近し、一緒に遊んでいくうちに心のつながりができ、回を重ねるに従い、あいさつや手をつなぐ等の行動の端々に小さな心づかいを何気なくやっている姿が見られ、わからないときには、手をとって教えてくれたり、ゲーム参加をしぶる子には、やさしく参加させようとはたらき、相手の気持ちをくみとろうとする姿が見られるよい交流になってきた。
本校児童には、健常児の身振りをみて体を動かす、手をつなぐ、集団を意識して場から離れなくなる、共に歓声をあげるなど集団への同調行動がたくさん見られるようになり、積極的な健常児へのかかわりも増え深まってきた。
表3 交流活動の内容
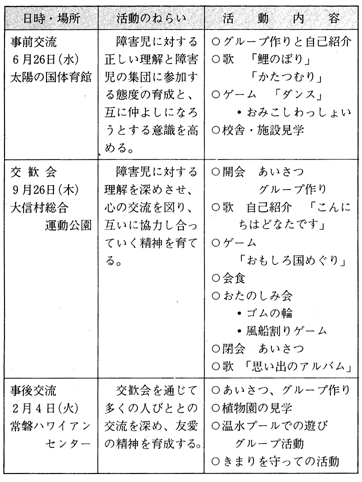
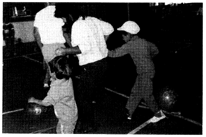
風船割りゲーム
(二) 児童作文(熊倉小三年Aさん)
1) 九月二十六日午前九時三十分、交歓会に行くため学校を出発しました。場所はたいしん村の運動公園です。さいしょに、ようご学校に行ってようご学校の人たちとバスにのってたいしん村の運動公園に行きました。わたしのあいては松本麻紀ちゃんです。麻紀ちゃんは、すぐ私に「どこでくうの」とききます。たぶんおひるごはんのことだなと私は思ったので、「ここでたべるんだよ」と教えてあげました。(中略)
そのうち、お昼になりました。手をあらっておべんとうをたべました。麻紀ちゃんにハンカチをかしてあげたりもしました。(中略)
ごごは、「おもしろ国めぐり」「ゴムのわのびろ」「ふうせんわりゲーム」もとても楽しかったです。ようご学校の人たちもみんな楽しそうでした。私は、もう一度交歓会をひらいてほしいと思いました。
2) (熊倉小三年Bさん)
養護学校に着いて、養護学校の人たちが次々に乗って来ました。わたしのとなりには女の子がすわ
|
|
|