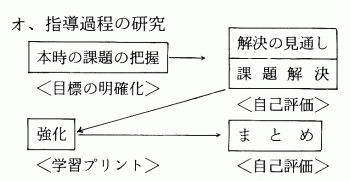|
段階 |
学習内容・活動 |
時間 |
指導上の留意点◎仮説との関連 |
|
課題把握 |
1.前時の学習内容について復習する
●X+3=6−2x
・移項
・同類項の計算
・等式の性質(4)
2.本時の課題を確認する
|
5 |
●移項のしかたを確めながらすすめる
◎前時の「自己評価票」の結果を参考にし下位の生徒を指名する
●ノートにきちんと書かせ課題をいっそう明確にさせる
|
|
解決の見通し・課題の解決 |
3.本時の課題の見通しをたて,解く
●2(x+1)=x+5
(1)解法手順を考える
(2)問題を解く
(3)解き方を発表する
4.類似問題を解き.手順を確認する
●3(x−5)=5x+1
●4(x+3)=7x−9
5.練習問題を解き,どこがつまずいているのか自己評価する
●4(x+2)=10
●5(x−3)=2x+3
|
20 |
●かっこをはずすと.既習の方程式となることに気付かせたい
●まちがいは指摘しあうようにさせる
●分配法則の適用にあたっては,特にかっこをはずす時.符号に注意する
●一斉に解き方を確認しながらすすめる
◎各自のつまずき.到達度を明らかにして、自己評価票に記入さていく
|
|
強化 |
6..練習問麗の到達度により,学習プリントで.コ一ス別学習をする
・2問正解・・・Cコース
・1問正解・・・Bコース
・0問正解・・・Aコース
|
15 |
◎コース別学習で,個に応じた学習をさせることにより,解決に習熟させ学力の定着を図りたい
●A、Bコースでは.はじめに補充問題を解かせ,つまずきを解消させるようにする
●机間巡視をし,個別指導をする。
|
|
まとめ |
7.本時のまとめをする
(1)確認テストの問題を解く
●2(x+3)=x+8
●3(x−2)=6−x
(2)かっこのある方程式の解法手順を再確認する
8.自己評価をする
・学習態度・理解度・確認テストの結果
9.次時の課題を知る
|
10 |
●本時のねらいが達成できたか確認させる
◎基本的な問題を出題し一人一人の生徒に成就感を味わわせたい
●下位の生徒に解法手順を発表させ,まとめをする
◎自己評価票に記入させ本時の学習態度をふり返らせるとともに,次時の学習意欲をかん起させたい
|