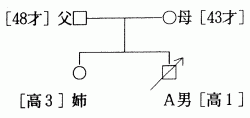学業不振から不登校となった生徒の事例
1.はじめに
今回の事例は,学業不振が原因で不登校になった高校1年男子A男が,各担当教師の協力的な指導援助によって,学校に適応していったケースです。
2.間題の概要
A男は高校入試の成績は比較的上位で入学してきた。また,自分の得意とする運動部に入部し,意欲的に練習していた。
しかし,6月に入り,上級生とのトラブルから部活動をやめ,同時に学校生活に対する意欲も薄れてきたように見られた。7月の期末考査の結果では,成績は大きく後退した。不良交友も始まっていた。
2学期になり,頭痛・腹痛・気分不快などを訴えて休むことが多くなった。「学校がおもしろくない」という訴えも聴かれるようになり,徐々に怠学傾向が強まった。
担任のK先生の精力的なかかわりにもかかわらず一進一退を続けていたが,10月になり,全く登校しない状態になった。そして,「退学して働きたい」と言いだした。
3.A男に関する資料
(1)家庭環境
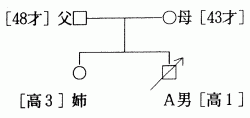
・父は厳格で,母は過干渉的。
・姉は進学校に在籍し大学進学を目指している。
・5年前に父が事業に失敗し,多額の借金を抱えた。一時期は苦しい生活が続いたが,現在は立ち直っている。
(2)成育歴
以前は,A男も成績優秀でスポーツ少年団で活躍するなど,快活な子供だった。父も長男ということでかわいがっていた。
しかし,父が事業に失敗した時を契機に不良交友が始まった。特に中学1・2年生の頃には怠学傾向も強まり,シンナー吸引で補導されることもあった。
それでも,中学3年生になると高校進学を意識するようになり,学校中心の生活に戻っていった。A男は普通高校への進学を希望したが,基礎学力不足のため,やむをえず実業高校へ進学することになった。
(3)性格
小さいころから神経質な子供で,きちんとしないと気がすまないところがあった。
きちょうめんで,完全癖が強い。
4.指導援助の実際
[指導援助の方針]
1.A男に
学校生活を続ける意欲を持たせる指導
を優先する。
2.担任のK先生がA男,教育相談係のM先生がA男の両親を担当し,生徒指導部主任のO先生が学校全体の連絡調整役を受け持つように
役割分担
する。
3.1学期の後半以降,A男の心境にどん