|
|
|
福島県教育センター所報ふくしま No.110(H06/1994.3) -010/038page
|
|
|
従来は,それぞれの教科について,それぞれの月毎の計算をしなければならなかった。
そこで1の作業において,プログラムを組むことによって月の時数(例では68時間)が分かれば,図2のように教科毎に配当するおおよその時数が算出されるようにした。
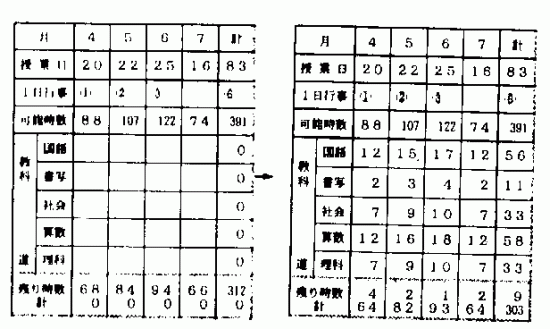
図2
また,2,3の調整は手間がかかると同時に計算ミスのでやすいところである。
そこで,プログラムを組むことにより図3のように,例えば算数の時数を変更すると月,学期,年間の合計が瞬時に変更されるようにした。
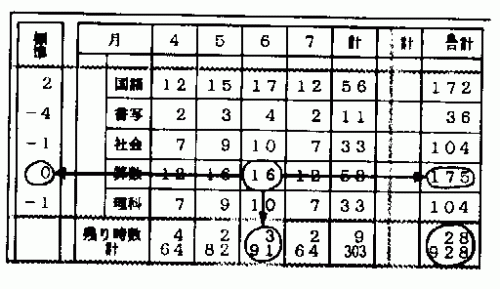
図3
6 考察
これらの試用によると,以前の時数集計作業と比較して,次のようなことがいえる。
(1)データ入力後,1回の計算が1分未満で可能であり,時間の短縮ができた。
(2)行事等様々な実施場面を想定した計画や時数案の検討ができた。
(3)データの入力さえ間違わなければ,集計処理上での計算ミスは生じない。
(4)データの入力は,最初の1回行うだけでよく,担当者の負担は軽滅できた。
(5)コンピュータ内で作成した集計表や月別計画は,すぐに印刷できるので,従前の編成作業の時間を著しく短縮できた。
以上のことから,今回の研究開発によって,時数集計関係の表を作り上げる段階での相当部分を手作業からコンピュータ処理化できた。このことは,当初ねらいとしていた教育課程編成時の時数計算の作業の,スピード化,効率化が実現できたことであり,開発の成果が得られたといえる。
7 今後の課題
(1) 今回のブログラムは,集計表としては基本的にはどの小学校でも利用できるものである。さらに,学校独自の集計スタイルがほしいなどの多様な要望に応じられるようプログラムの改良を図りたい。
(2)今回の開発研究は,教育課程編成時の時数集計関係の表を作成する段階にコンピュータをどう利用していけばよいかという点に限って研究開発を進めてきたが,今後は,教科の進度を適切に把握する上での時数管理のためのプログラム開発と,時数管理以外にコンピュータを利用した教育課程の編成,例えば,教科の単元配列表の作成ブログラムの開発にも取り組んでいきたい。
(協力校 白河市立白河第一小学校)
|
|
|